
本記事では「警察官を辞める人物の特徴」と「警察官の転職事情」について解説します。
警察官を辞める人物の特徴
著者が警察官として勤務した経験から「退職する」人物の特徴をピックアップしました。
以下の項目に当てはまる人物は慎重に進路を検討しましょう。
正義感が強い人物

正義感が強い人物は警察官には適していません。
それでは、具体的に正義感とは「何」を指すのでしょうか。
それは、個人の「胸の内」に秘めた感情です。
噛み砕いて解説するのであれば、個人が憤りを感じることに対する嫌悪感が正義感の正体です。この嫌悪感に対する防御反応が正義感として現れます。
つまり、自己が不快に感じる現象を排除する反応(心の平穏を保つため)が正義感だと言えます。
正義感は誰しもが抱く感情です。
誰もがニュースや新聞を通して「なんて酷いことを」と感じたことがあると思います。
この「憤り」が正義感です。
そして、「憤り」を分解すると「どうにかしたい」など、行為に移したいとする欲求が少なからず心の奥深くには生まれます。
正義感の強弱は「憤り」の大小でも測ることが出来ますが、「感情」を「行為」として表す度合いの大きさが際立つほどに「正義感が強い」と言えるのではないでしょうか。
正義感が生み出される過程には物事の「定義付け」が必須の条件となります。
これは、「この限度を超えた行為は悪である」とする自己の内に定める基準です。
この基準を逸脱した対象を攻撃する機能が「正義感」には備わっています。正義感を満たすためには行動に移すことが重要であり、正義感の根幹である気持ち(不快感による心的ストレス)に対抗する防衛機能として作用します。正義は宗教と似たような性質を持ち、自分の信仰する正義の尺度は誰かに布教してしまうものです。
正義感としての感情を充足させるために表面化する「行為」である「攻撃する機能」の大小が感情の起伏と比例します。
なので「正義感」が「強い」とは、「攻撃する機能」が高いことを意味します。
自己に抱く正義感が普遍的な概念を持たず包括的な基準に左右されるのであれば、それは正義感の意味を為しません。

良い言い方をすれば正義感、悪い言い方をすれば頑固、それが正義感が強い人物です。
これら「正義感」は個人の「感情」が原動力(軸)として、個々の言動(行為)を掌握するものですから、もちろん、統一的な正義感の見解は存在しません。
なので、正義感の定義は人により変化します。
殺人事件に対して憤りを感じる人、交通事故に対して憤りを感じる人、不倫報道に憤りを感じる人、殺人事件には憤りを感じるが不倫報道には興味を示さず、交通事故には憤りを感じるが殺人事件に対しては感心を示さないなど、個々の人物が情報を処理して感情に変換する上でその捉え方は異なります。そうすると、必然的に各々の人物が反応として表す行動(行為)も変わってくるのです。
人間は、この感情を基礎(善悪の判断)にした相手の行動を読み取り類似した性質を有する人物同士でコミニティを形成します。その結果として、外界から刺激を受容した場合に共通した感情を享受できる個体同士であれば円滑な統率が実現できることから生存率が上がるとの戦略です。
正義感は人間の表面上に現れる性質を顕著にする手段であり、これに共鳴した人々が同調する生存戦略が狙いなのです。
ですから、警察が求めている正義感を有する人物であれば、そのコミニティに歓迎されます。
正義感とは、各々で抱く感情やそれに伴う価値観の名称です。なので、異なる価値観を軸としたコミニティに属することは自己又はコミニティの不利益になります。
著者は、警察官として勤務していた際にサービス残業をさせられていました。
地域警察官として警察署に配属されると、勤務時間前に道場に通い柔道又は剣道の稽古を強制されます。警視庁では午前8時30分が就業時間なのですが、実際には午前7時頃には出勤をして剣道又は柔道の訓練をしています。さらには、退勤時間である午後5時15分を過ぎてもゴミ捨て等の雑用から実際の退勤時間は午後6時頃となります。
これらは全て無給なのですから驚きです。
著者は、このような慣習に対して憤りを感じていましたので、自身の内では正義感から我慢ならない気持ちになりました。
しかし、他の署員を見てみると柔道や剣道の稽古は警察官として必要であるため無給の労働でも厭わないとする考え方が浸透しており、彼らの正義感はここにあるのです(犯人を制圧するためなどの正義の執行に伴う鍛錬である過程も、また正義感の範疇にある行為だと考えている)。
著者はサービス残業は違法故に許せないとする正義感、他の署員は職務遂行に欠かせない技能故にサービス労働は必要とする正義感、どちらも正義感に基づく感情です。
しかし、その正義感は相容れる性質ではないため、コミニティにおいては多数派たる正義感が生き残り他の価値観は淘汰されます。
正義感は感情の起伏により生じるメカニズムであるため、その自己の定義たる行為が実現できない状況においては「不快感」を抱きます。
そもそも、正義感とは自己に生じる「不快感」(心的ストレス)を軽減するための防御反応が行為として現れる状態です。
なので、自己が掲げる正義感が否定される状況で他者の正義感が尊重される環境では心的な負荷が大きくなります。
正義感が強い人物は、自己の心的欲求を充足させる過程において、その「行為」が妨げられる又は遂行できない状況を嫌います。
正義感が強いと、そのコミニティが主軸とする価値観と異なる場合においては、相当なストレスになるのです。
警察組織では、ある一定の性質である正義感を主軸として強い同調圧力が存在しています。前述の事例で言うのであればサービス労働をすることに対して疑問を持たずに順応する人物のほうが多数派でしょう。となると、サービス労働に対して憤りを覚える人物の正義感は淘汰されます。
警察を構成する人々の価値観である正義感の傾向に沿う人物であれば、その正義感を活かすことは容易ですが、組織の方針に沿わない正義感を持つ人物は排斥される可能性が高いことから、強い正義感を抱いている人物は退職する傾向が多いのです。
さらに、自己の正義感が否定されることで、他者が強要する正義感(別の考え方)を迎合しなければならず、そんな仕事や職場環境に対して不平不満を抱くようになります。
警察官として定年まで働きたいのであれば、正義感よりも柔軟性による適者生存が大切であると言えるのです。

正義感のために遂行したい「行為」と相手(警察組織)が求めている(してほしい)「行為」が合致することがベストの状態です。
仕事に対するリスペクトがない人物
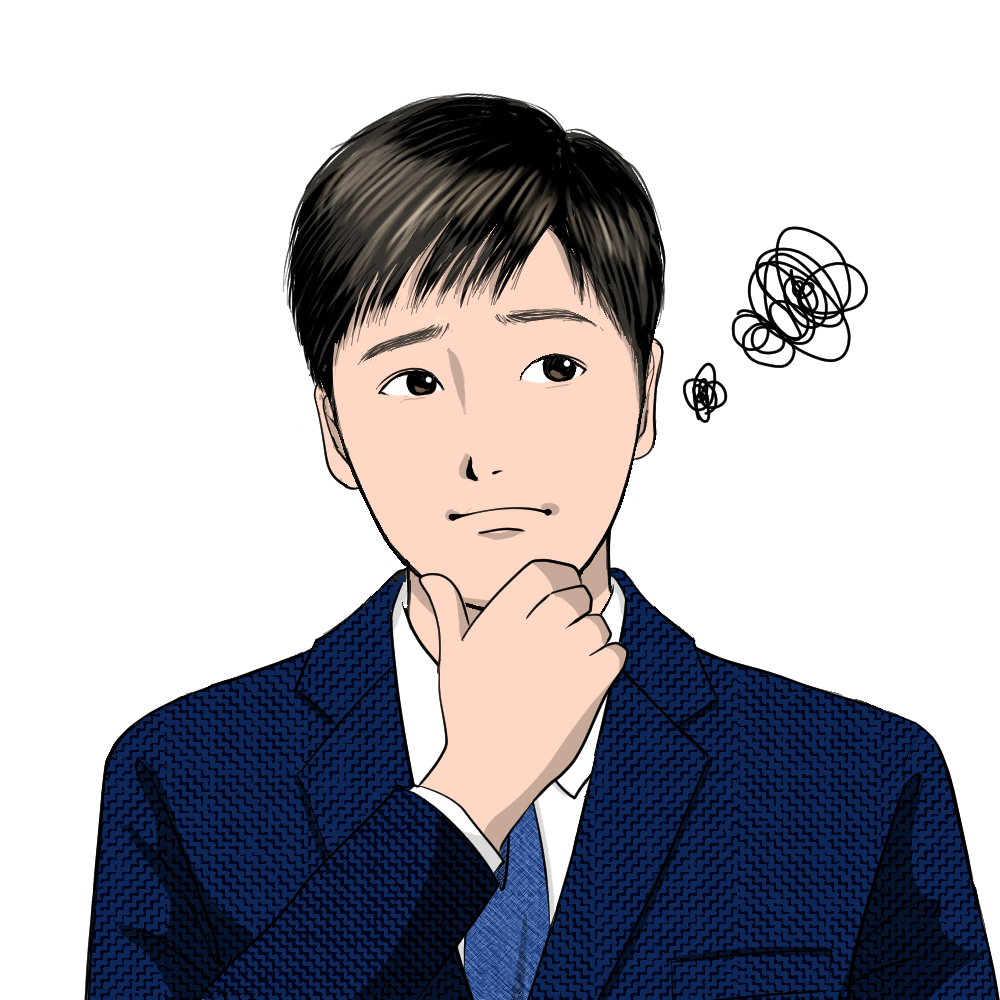
警察官なんて取るに足らない仕事だよ。
警察に対して批判的な考えを抱いている人物は退職する傾向が多いと言えます。
組織批判や不平不満を口にする人物、警察の方針や制度、働き方に疑問がある人物も同様です。
このような人物は警察官を辞めます。
さらに、警察官として採用される前から警察官の身分について敷居が低いもの(プライドを持てない)と考えている人物の多くは退職をしています。
具体的には、警察官になるために特別な努力をしていない人物等が挙げられます。

その理由を詳しく解説します。
警察組織は官僚主義です。
官僚主義に欠かせない要素とは権威です。
権威とは、強者が弱者を管理するために用いる道具を意味します。
この道具は、非支配層がより効果的に支配層に従う仕組みであるほど完成されていると言えます。
また、権威とは、非支配層から認知されず無意識に介在する要素でなければ意味を為しません。
例えば、子供は大人の指示に従います。
その理由は、子供は大人に従うとの基本的な秩序が自然と刷り込まれているからです。
この自然的な摂理に懐疑的な感情を持つと「子供は大人に従うもの」との基本的な秩序は崩壊します。
ですから、他者を統率する道具たる権威は人間の無意識下に組み込む必要があります。
宗教でも信仰心が重要なように、人々のコミュニティたる社会や組織の秩序を維持するためは権威が必須な要素です。
宗教は信仰心から始まります。
組織も権威がなくては成立しません。
人間の無意識に存在する「従わなければならない」とする感覚が権威の正体なのです。
警察を含む官僚主義社会では、構成員を統括する権威として、身分の優劣を階級や年功(年次)による序列で管理しています。
なので、官僚主義の構成員たる公務員は既存の権威である制度や方針に対する信仰を放棄して懐疑的な感情を抱くようでは、権威により管理されるコミュニティにおける構成員としての資質がありません。
官僚主義が成立する本質は、あくまで官僚制を信奉する人々が存在する前提から権威が生じることにあるので、無意識の権威を可視化してしまう人物は官僚制が統率できる範囲から逸脱するため警察官に限らず年功序列や階級社会には馴染めないでしょう。
さらに、権威に迎合される資質は無意識に生じる気持ちの尺度に影響しますから、警察組織に対する批判的な姿勢は官僚主義に相容れません。

警察官の仕事は「誰でも」できます。だからこそ「気持ち」が大切なのです。その「気持ち」の大小を図る手段が採用時点のモチベーションです。なので、警察官の試験を受ける段階で特別な努力をせず「なんとなく」で採用された人物は退職をするのです。
官僚主義の権威たる階級社会や年功序列の体制が維持される理由として、画一化された仕事内容であることが挙げられます。
誰であろうとも仕事を教えれば一定の成果を出せる内容であるからこそ、階級社会や年功序列は成立します。
無から価値を想像する仕事においては官僚社会は馴染みません。
なぜなら、権威たる統治手法では価値を想像する工程に関しては妨げになるからです。
官僚主義が統率力を最大限に発揮できる環境とは「教わる」人物たる非支配層と「教える」人物である支配層が明確に分離した社会における個々の意見を排斥した形態です。「誰にでもできる仕事」を言い換えるのであれば「誰もが教わることで一定の成果を収めることのできる仕事」です。
なので、必然的に「学ぶ側」と「教える側」の立場が明確化されて、受動的な非支配層を効率的に統率するために権威による管理が台頭します。
これら、権威により成り立つ仕事はモチベーションたる「気持ち」が重要です。
新たな価値を想像する仕事では「教える主体」が存在しないため、突発的な発見又は先天的な才能や能力から生じる価値が評価される仕組みであるため、努力や気持ちの強弱とは異なる原理から利益が生まれます。
けども、権威が後押しする仕事は立場が明確化されているため(予定調和的な物事はするべきことが判然としているので努力量と成果の相関性が高い)学ぶ姿勢としての気持ちが大きいほど評価に繋がるのです。
学ぶことが主体となる警察官の仕事においては「気持ち」が重要です。
仕事に対する熱意がなければ、学ぶことが主軸な仕事では内容が身に付かずにプラスの評価はされません。
さらに、警察官の仕事は過酷です。
非番には酷い頭痛と倦怠感が身体を蝕みます。
そんな過酷な仕事を継続するために重要となることも「気持ち」です。
警察官は、他の職業と比較しても過酷な内容です。
そのため、本人の仕事に対する熱意が過酷な仕事をポジティブな意識に後押しをします。
このような状況を流行りの言葉で表現するのであれば、「やりがい搾取」と定義できるのですが、過酷な仕事に耐えるためには神聖的な仕事であると盲目的になる必要があるのです。
悪く表現するのであれば選民思想的な使命感が求められているのでしょう。
自分は警察官であることを許された特別な存在だとする気持ち、その感情がモチベーションを育みます。
そして、その過程は、採用における段階で努力した人物でなければ得られません。
個々の能力が高いことを理由に内定した人物は数ある選択肢の一つとして警察官を選択しているため、その職業に従事する特別感は少ないでしょう。
そのため、権威主義たる官僚制に疑問を呈したり、気持ちが上擦ることで組織との価値観の相違から退職をするのです。
やる気がない
これだけは言わせてください。

仕事に対する「やる気」がないと長続きしません。
それもそのはず。
警察官の仕事は精神的にも、身体的にも、過酷な公務です。
そんな「辛い」仕事を継続するために必要なモチベーションである「やる気」がなければ挫折します。
なので、警察官の仕事が「好き」でなければ務まりません。
著者の経験を紹介します。
私は警視庁に採用されてから警察学校を卒業して、現場である警察署の地域課に着任しました。
地域課では、主に交番やパトカー乗務員として勤務するのですが、そこでは職務質問による検挙が評価されていました。
この職務質問による検挙は通称「職質検挙」と呼ばれており、一般的な企業で言うならば「営業」で「契約」を結ぶようなものです。
そのため、地域警察官の仕事は「職質検挙」であると言っても過言ではありません。
そんな、職務質問ですが、私も実務1年目にして検挙することができました。
しかし、はじめての検挙ですら達成感を感じることはなく同僚が「おめでとう」と労う最中の心中では「給料も変わらないのに仕事を増やしたくないな」と考えていました。
地域警察官は「職質検挙」による「件数」を競う傾向にありますが、誰が「職質検挙」をしようとも興味を抱くことができず、その温度差から私は警察を後にしたのです。
警察官は公務員ですから、仕事をしても、仕事をしなくても、待遇の変化は些細なものです。むしろ、積極的に働くことで損をします。
警察の仕事は「辛い」ことばかりです。
時には休憩や休日を削り仕事をしなければなりません。
それこそ「職質検挙」のために「休憩時間」を削る状況も往々にしてあります。
もちろん、その時間の手当は支給されません。
自発的に仕事に取り組んだ旨の形式として処理されるのです。
警察官として勤務していると、このようなことが多く強要されます。
そこでも、仕事に対するモチベーションが重要になります。
仕事に対する「モチベーション」があるからこそ、それを目標や楽しみに努力ができるのです。
さらに、これら「やる気」が人物査定の評価につながります。なので、警察官の職場環境において、やる気がないと評価されない状況から嫌われます(居心地が悪くなる)。
警察官として勤務する上で、将来の希望(「刑事になりたい」とか)がなく、仕事の中で楽しみを見つけることができない人物は長続きしないでしょう。
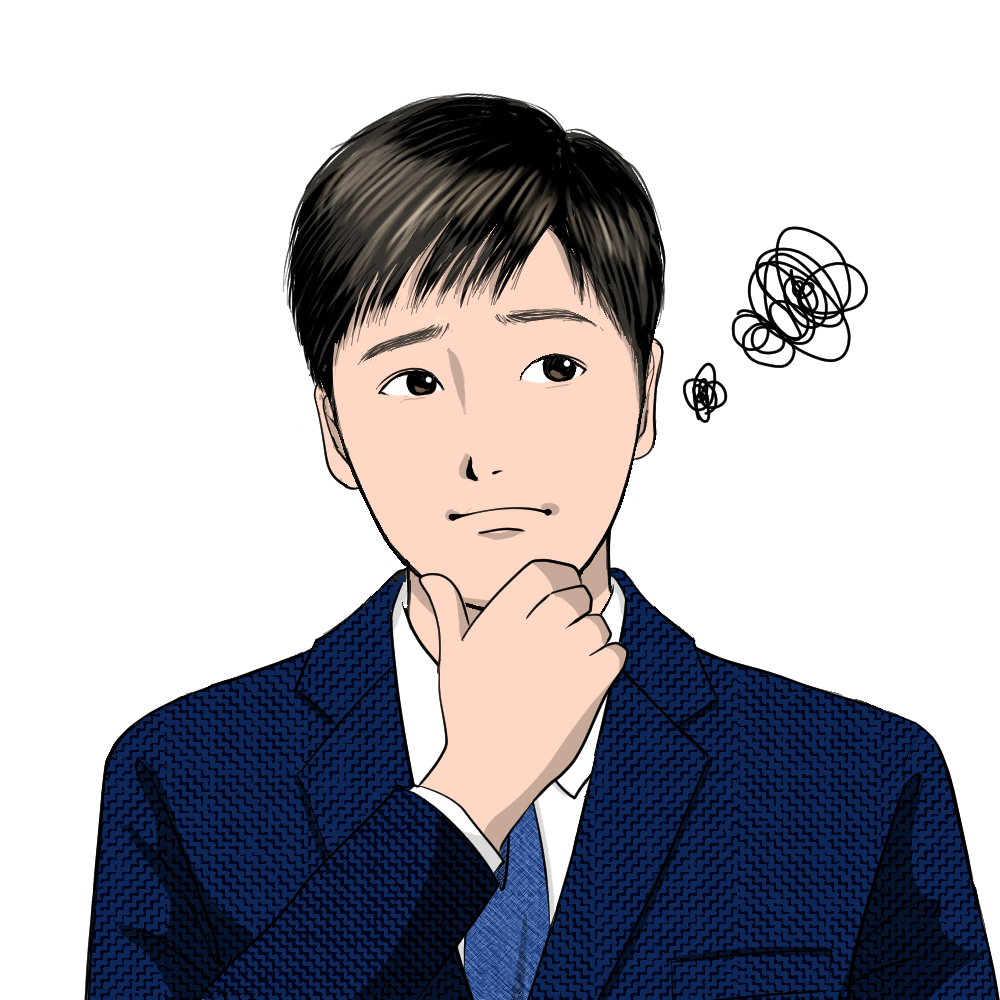
なんとなく「警察官」になると続かないのかな。
職業を選択する上で重要なことは「適性」です。
著者の見解では、職業の適性は「なれる」と「向いている」これら要素が関係しています。
警察官の仕事に対する「やる気」があっても適性に問題があれば良い選択とは言えません。
されに、仕事に対する「やる気」も、採用される以前の段階ならば「創造」でしかなく、その架空の仕事を対象にして「やりたい」とモチベーションを高めている状態です。
こればかりは、採用されてから実際に警察官の仕事を経験してみなければ判断できるものではないように思えます。
学校が嫌いな人物
警察官の採用試験に合格すると警察学校に入校することが認められます。
警察学校の名称にも「学校」が付いているように、警察学校とは学校教育の延長線に位置する環境です。
「教場」と呼ばれる「教室」には「先生」すなわち「教官」が「生徒」である「巡査警官」を指導します。
学校教育での「生徒」と「先生」の関係と同じです。
警察学校に限らず警察官として現場に出てからも、これら学校的な雰囲気は続きます。「先生」から「先輩」、「上司」になるだけで、根本的な環境は変わらないのです。
そのため、学校教育における主従関係や受動的なカリキュラムに適応することができない人物は、それと同じく警察組織でも馴染むことも難しいと言えます。
ここで示す学校教育に馴染むことができない人物とは、制度等の体制に対する疑問や機械的な教育の過程に適さない性質を有することであるため、人間関係等の外的要因(いじめ等)から学校に馴染めない場合は含みません。

前項で解説した「教える側」と「教えられる側」が明確に定義された環境で「与えられた課題」に取り組むことが得意(与えられる環境から能力を発揮する人物)な人物は学校的な制度と相性が良いと言えます。反対に、能動的に自己が取り組むべき「課題」を定義したり、新たな価値を想像することが得意(自由な環境で能力を発揮する人物)な人物は学校的環境が足枷となります。
学校教育は「みんな」と同じ価値観を享有することが望ましいとされています。他者と共通の価値観を享有する環境では、そこに存在する慣習や規律等のコミニティを統率するために必要な秩序も共通の価値観として内在するため、そのコミニティでは自己の行動規範を他者に依存させます。本来であれば、行動や思考の意思決定権(アイスを食べる=私がアイスを食べたいから)は自己に帰属するのですが、現在の教育では調和に欠かせない相互の共通項を享有(アイスを食べる=みんながアイスを食べているから、みんなの好物がアイスだから)する構造がコミニティを統率する基本原理として確立しています。
みんな「努力」してるから「努力」する。
みんなが「我慢」しているから「我慢」する。
これが、日本の社会形成における基本的原理です。
人間は社会的な動物であるためコミニティを形成します。その過程において、互いの共通点を無意識で擦り合わせることで効率的に社会の形成が促進されるのです。なので、自分の思考や行動に他者の価値観が混在(影響)してしまう状況は、ある程度であれば許容できます。しかし、本来はコミニティの形成に必要な価値観の享有や擦り合わせる作業は性質が類似する個体同士を結ぶための手段であるため、あえて自己を同調(所属する予定のコミニティと同じ性質に自分を同調)させる逆説的な現象には疑問が生じます。独立した思考や行動を他者や環境に委ねている状態は動物には持たない「人間らしさ」を放棄しているのではないのでしょうか。
人間は「社会的な動物」だと言われます。
しかし、社会性たる秩序を維持するためには個々の価値観をコミニティに譲渡する必要があるため、本質的な意味において「自由の刑」に科せられている人間は稀なのだと考えます。

「自分は自分である」「他人は他人である」
このような考え方をする人物は公務員には適さないと思います。
このように考える人物は集団で群れることを嫌います。
著者も、学校教育における「同調文化」に馴染めない人間でした。
「みんなしてるよ」
「みんな〇〇だよ」
学校の先生から言われた言葉です。
その度に理解に苦しみました。
「だから何だ」と。
どうして私の行動や思考が他者の気持ちに影響を及ぼすのか、なぜ影響を伝播させようとするのか、自己の感情は自己の責任で管理されるべき。個々の行動や思考が他者の権利や名誉を侵害しない範囲において個人の感情や感傷も独立して自己の責任で処理されるべき。そう考えていました。
しかし、社会的な規範を有する人々は個々の感情も他者が負う責任だと認識をしています。その価値観(同調文化)を扇動する権威たる先生や先輩然り慣習に従順たる学生(人間)も秩序ある社会には欠かせません。
警察官は「誰にでもできる仕事」です。
しかし、それは専門性を有しないことを「誰にでもできる」と定義しているため、精神的又は感情(気持ち)において「向き不向き」は明確に分かれます。
そんな「誰にでもできる」仕事だからこそ、学校教育を彷彿とさせる職場環境だと言えるのです。

「誰にでもできる」とは、誰かから「教わること」で内容を理解して活躍することが出来る仕事です。なので、必然的に「教わる側」と「教える側」の立場に優劣が明白に定まることで、学校教育のような環境、「先生」と「生徒」の関係が職場でも続くのです。
学校教育に適用できない人物は警察官として長く務めることは難しいと思います。
無駄が嫌いな人・古い慣習に懐疑的な人
警察官の仕事は無駄なことが多くあります。
その理由は、仕事を行う上では前向きな気持ちが重要であり、それが評価に結び付くからです。
無駄なことの具体例とは、職場の人間関係を円滑化する目的から生じる行為です。
仕事の効率性よりも人間関係の維持が優先される警察社会では、これらが競合する場面のおいて仕事の合理性や効率性は度外視されます。
警察官の仕事は「誰にでもできる」内容です。
ですが、これは同時に「誰かから教えてもらわなければ」仕事をすることが「できない」との意味も含みます。
そのため、「教える側」と「教わる側」の立場が明確化することで、円滑なコミュニケーションの構築が仕事のパフォーマンスに繋がるのです。
新人は、仕事を上司や先輩から「教えてもらう」前提がなければ、職務として成立しません。
そのことから、「教えてもらう」立場にある新人は、仕事を習得するために人間関係の維持(良好な関係)を心掛けます。
となると、必然的に「教える側」は抽象的な概念である気持ちを評価するようになります。
なので「教わる側」は仕事を覚える過程でコミュニケーション、言い換えれば「媚を売る」ことにより人間関係を促進するのです。
著者の警察官としての経験を挙げると「先輩より早く出勤しなければならない」とする暗黙の掟がありました。
新米警察官として警察署に配属されると装備品や書類の準備のために就業時間より早めに出勤するのですが、その作業が時間に間に合うように計画(出勤)しているのにも関わらず、先輩がその時刻より早く出勤することで、著者もさらに早く出勤することを強制されました。
また、警察社会では「体裁」を重んじる傾向から「合理的」に考えて「無意味」なことも強要されます。
物事における効率性や合理性を追求すれば、無駄な行為ではあるのですが、そんな無意味で生産性がない行為に意味を持たせるのが警察社会です。
他者に対する過度な配慮や気を遣う行為は「気持ち」を重要視する職場ならではの文化でしょう。
このように、仕事を熟す過程で「合理性」や「効率性」を追求する行為は、人間関係を構築する手段たる慣習や感情が優先される警察社会では歓迎されません。
もちろん、これら「気持ち」から「評価」に結びつく職場の環境を踏まえると、その行為は無駄とは言えないのですが、ある目的(装備品や書類の準備をする)を達成する過程において、主軸とは異なる影響(コミュニケーションによる人間関係の円滑化)が内在して、目的が蔑ろ(本当の目的〈 主軸とは異なる意味)となる自体に主眼を置けば、無駄なことが多い職場であると思います。
考え方として、「効率的に」「合理的に」を意識する人物は、ビジネスの場面で活躍できる素養が高いので公務員は適さないように感じます。
【ビジネスには欠かせない簡略化の思考】

「給料が変わらないなら。。。」
何をしても給料が同じならば「必要最低限の努力をしよう」が賢い考え方だ。
無駄なことが嫌いな人物は物事を功利的な視点から見るので、損得勘定によって自己に生じる利益を考えます。
必要最低限の労力で最大限の資本を得る。
この考え方はビジネスの基本です。
無駄な行為に対して嫌悪感を示す人物は資本主義が発揮される環境において充分な評価が期待できる素質があります。

慣習や既存の価値観に懐疑的な人物も要注意です。
既存の価値観や慣習に懐疑的な感情を抱く人物は珍しいと言えます。
価値観や慣習は最大多数の人々が好ましいとする意思が享有されて形作られた概念です。なので、疑問を持つ行為自体が最大多数とは異なる性質を有する人物であるとの裏付けなのです。
多くの人々が容認してきた慣習や価値観の不備に気が付いてしまうことを理由に懐疑的な感情が芽生えるのですから、その発見は正義感と同じく誰からも肯定されず自己が介入できる範疇にない場合は満たされない欲求から、残るは「負の感情」のみです。
警察では、これら無駄な行為と並行して慣習や価値観を重んじる傾向があります。
その理由は官僚社会の短所たる保守的要因に作用されるものですが、その構造が変わることはありません。
なので、慣習や既存の価値観に自己の意思を左右されることに嫌悪感を示す人物は警察社会では馴染まないでしょう。
大雑把な人物
大雑把な人物は警察官の仕事には合わないでしょう。
警察官の仕事は書類作成がその業務の大部分を占めます。
この書類作成ですが「こんなことも気にするのか」という箇所まで細かい書類作成技能を要求されます。
警察官が作成する書類は司法書類であるため、裁判における証拠に成り得るものです。
なので、書類に不備があるようならば裁判で指摘(被疑者側の弁護士)されます。
極端な例えですが、凶悪犯を逮捕したと仮定して警察官が作成する書類に不備があることを理由に裁判にて無罪放免とされては目も当てられません。
そのため、警察官が作成する書類には大きな影響力があり、また、職場でも厳しく指導される内容なのです。
さらに、書類作成に限らず身だしなみを含むマナーや言動を細かく指摘されます。
そんな「誰も気にしないだろう」という箇所を過敏に気にして外面ばかりを意識する人物は警察官として勤め上げることが出来ると思います。

警察官の仕事は形式を重んじる傾向があるので、意味さえ伝われば良くない?と考えている人物は向いていません。
また、オリジナリティを発揮してデザインやイラスト、文章の構成を自由に考えて書類を作成する(プレゼン的な)内容の仕事は非常に少ないと言えます。決められた書式や既存の書類、これらを真似して書類を作成する能力が求められます。なので、新しいことに取り組みたい人物よりも、従来の慣習を辿ることが得意な人物が警察官の仕事には適しているでしょう。
著者が警察官を辞めた理由の一つとして仕事に興味を持てなかったことが挙げられます。
学校教育のように、教科書の内容をノートに転写する作業に面白みを感じなかったからです。
世の中には「自由な環境で能力を発揮する人物」と「与えられた環境内で能力を発揮する人物」に分かれます。
どちらにも長所と短所が存在するため、優劣はありません。
警察官の仕事は「与えられた環境内で能力を発揮する人物」が評価される内容です。
どちらが得意なのか自分の特性を理解しましょう。

今回は「大雑把の人物」を議題の主軸にしました。しかし、人間は誰しもが大雑把であり繊細でもあるのです。
人間は興味があることや価値が高いと感じることに関しては繊細であり、興味がないことや価値を見出せないことに関しては大雑把になるのです。
著者は幼少期から容姿には無関心でした。
そのため、私服は数えるほどしか持ってはおらず、汚れたりしても気にせず着用していました。
これに関して、他人は大雑把と非難しますが、著者からすると繊細だなと感じます。
では、著者の性格は大雑把なのでしょうか。
これまた違うようです。
著者の友人は私を神経質だと指摘します。
その理由は、会話において理屈を並べるからです。他人からすれば会話の矛盾的を指摘してくるめんどくさいやつと思われているのでしょう。
しかし、著者の感覚からすると「矛盾点」は「繊細」なことではなく、その相手が「大雑把」であると感じてしまうのです。

イジメの構造と大雑把な性質の考え方は似ています。
イジメられる人物は「普通ではないこと」がその行為の対象となることが多いです。
そして、加害者は「他人の普通ではない箇所」を発見するプロです。
どんな些細なことでも「大多数」とは異なる特徴を見つけてそれを理由に被害者をイジメます。
このメカニズムは、イジメの被害者からしたら取るに足りない事柄でも加害者を含む大多数の価値観から見ると着目するべき内容である場合です。そこの差異が「普通」ではないとの基準を定義付ける材料となりイジメに繋がります。また、普通ではないと定義する人物は大多数が普通であるとする価値観を享有しているので、その環境における自己の裁量(自己の価値観と大多数の考え方が一致)が基準として成立するのです。
なので、普通の人々とは異なる価値観を有する人物は人間関係において苦労します。
著者の事例を挙げるのであれば、大多数は容姿に関して価値を見出していて、著者は大雑把(普通ではない)であると非難される構造が当てはまります。
端的に説明するのであれば、大多数の人間が気にする箇所に対しては無関心(大雑把)であるという意味です。
これを理由に、自己が属するコミニティ(大多数)が享有する価値観とは異なる基準を有する人物は馴染めないのです。
警察は「普通」の人間が採用される仕組みです。
そのため、「普通」を享有する人物と感覚や価値観が異なる場合は、警察官として働く上で人間関係において苦労すると思います。
自分からしたら「当たり前」の価値観でも、他者である大多数の人々からは大雑把や繊細であると非難されて矯正を強要されるのですから相当なストレスです。
イジメと同じく「普通ではないこと」を発見する能力は書類作成においても役に立ちます。
そのコミニティの価値観からしたら「当たり前」だとする内容でも、普通ではない(大多数とは異なる価値観を持つ人物)ことから「取るに足りない内容」であると無意識に処理をしてしまうことで、誰もができる仕事でも上手く熟せない等の弊害が生じます。
警察官の書類作成は細かい部分まで添削されるのですが、その違いを発見(細かい書類の不備)して改善していける能力も「普通」とは異なる特徴を感じ取れる感性なのでしょう。
言われたことができない人物
どこの仕事でも「言われたことができない人物」は職場で苦労します。
上司や先輩から「何で出来ないの」「前も教えたよね」と叱咤される日々に頭を抱えて辞めていくのです。
しかし、仕事を覚えられない理由を上司や先輩から尋ねられても「できない」のですから仕方がありません。
かく言う著書もそんな一人でした。
ですが、「言われたことができない」とは、その対象とする物事に限定されることです。
なので、職場で「言われたことができない」と責められても悩む必要はありません。
著書は、警察官として採用されてから怒られてばかりの毎日でした。
その内容は「言われたことができない」ことが原因の多くを占めます。
出勤するたびに「身だしなみ」の指摘や、勤務では書類上の指摘が重なりました。
そもそも、言われたことができない理由は、言われたことを「忘れてしまう」ことにあります。
これは、その対象に関する感心が薄く価値を見出していないから「忘れてしまう」のです。
身だしなみを指摘されても「自分の中ではどうでもいいこと」であると無意識に処理しているので疎かになるのです。
これら、物事に序列を付けて処理する機能は個人の「価値観の違い」に由来するものなので改善は難しいと言えます。
著書は、現在の仕事からシンポジウムに参加したり、大学生と交流する機会があるのですが、そこでは「なんでこんなことも分からないの」「さっき説明した理屈じゃん」と頭を抱えることがあります。
しかし、それは相手が「言われたことができない」のではなく、その対象となる分野が不必要であると脳内で無意識に処理した結果なのです。
つまり、個人の「適正(向き不向き)」が左右する問題です。
向いていない事柄に対して「言われたことができない」ことは当然ですし、個人が得意とする分野であれば「覚えが早い」のも当たり前です。
なので、職場において「言われたことができない」と他人と比べて指摘される場面が多い人物は、その組織では価値観や適正が合わないのでしょう。
無理に改善するよりも「価値観や適正」が合う環境で働くことが無難であると著書は考えます。
ここからは警察官として勤務する上で「言われたことができない」と評価されてしまう人物について解説します。
それは、義務教育を始めとした学校制度に馴染めなかった人物が挙げられます。
その理由は、良くも悪くも警察官は「普通」の人物で構成される組織であり、多くの人間が集まる学校では平均化された価値観や能力を有する人物がシステムに馴染むことは必然です。
なので、そんな普通の価値観から構成される警察の環境に類似した学校で上手く立ち回ることができない人物は、恐らく興味や感心を示す主体が異なることから「言われたことができない」と評価されることでしょう。
他にも、知能的な問題から「言われたことができない」場合もあります。
職場で友人を作れない人物

著者の経験から語ります。
「類は友を呼ぶ」このような言葉があるように「会社」であっても、その特徴に合う「個人」が集まります。
そのため、職場の人間関係を大切にできない人物はその組織で長く務めることは難しいと思います。
著者の経験にはなりますが、どのように努力しても職場の人間との関係が楽しいと思えず、最終的には転職をしました。
警察官になると、多くの人物は職業の特殊性から人間関係も限定的になる傾向があります。
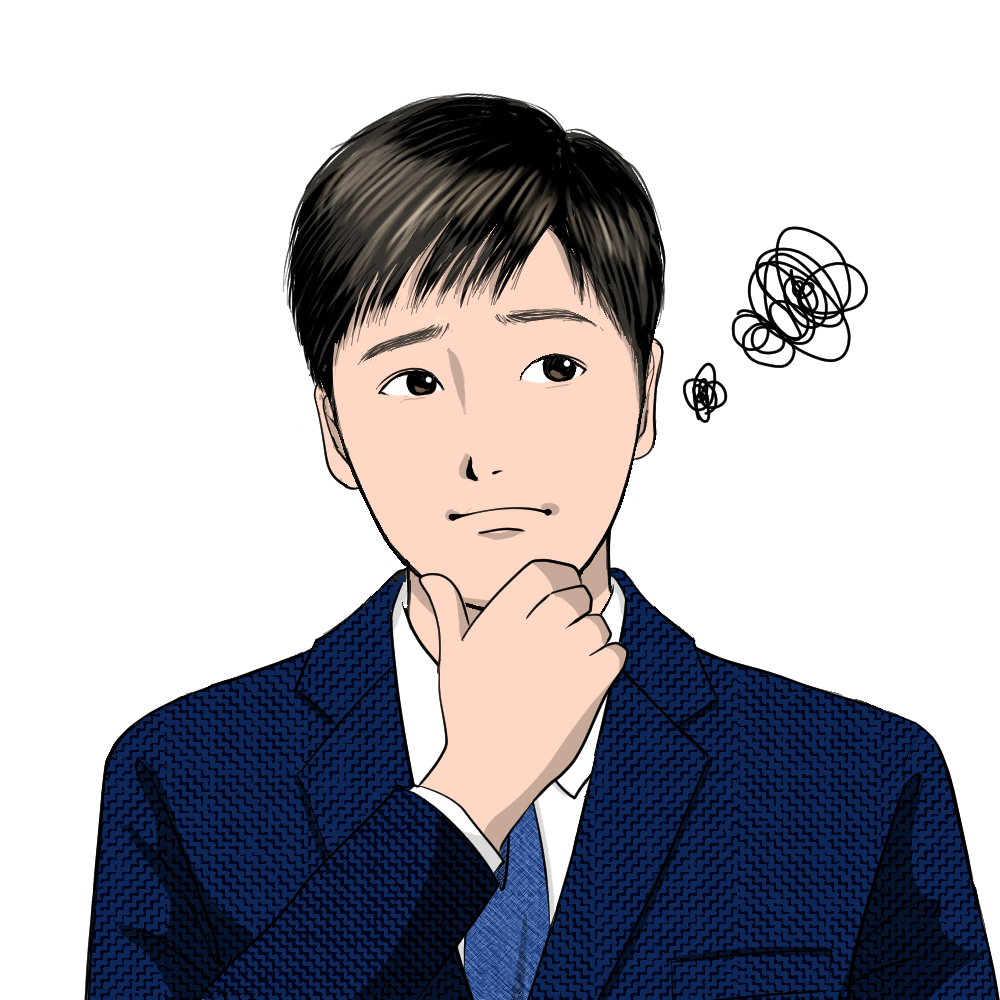
そのほうが会話が捗るし気が合うんだよな。
けども、そんな環境の最中で仕事とプライベートで接する人間関係を明白に分けている人物は少なからず警察官として働くことに対する違和感を抱えているはずです。
人間は、仕事での性格よりもプライベートで見せる姿が本質的(素の自分)であると言えます。そのため、素の自分と職場の自分との乖離が大きく広がるほどにストレスを抱えることになります。
職場の関係を楽しめない人物やプライベートに同僚や先輩と関わりたくないと考えている人物は転職を勧めます。
著者も、仕事以外の時間を同期や先輩のために費やすことに対する不快感が大きく、プライベートの会話でも価値観が異なることから全く会話が噛み合いませんでした。
なので、警視庁に就職してからは、大学の友人や副業関係で知り合った人物との交流を優先していました。
そうなると、自然と他の環境や業界に惹かれるものです。
警察官として採用される前であれば、警察から採用された人物や警察官を目指している人物と接してみることで擬似的に警察官として働く上での人間関係を体感することが可能です。
どんな人物が属するコミニティなのか予習する意味でも大切ですし、早い段階で自分と合う環境なのかを検証できるので勧めます。
職場で「気が合う人物」がいない。
これと同じく、職場で「尊敬できる人」が見つからない場合も、その仕事を辞める予兆であると思います。
尊敬できる人が見つからない理由は、「優秀」と評価される人物が「どんなに仕事ができても」その内容に興味や関心がないことで、その成果に見合う評価や感情を示す対象にならないからです。
なので、職場において「尊敬できる人」が存在しないのであれば、その仕事に興味や関心を持てない証拠でもあるのです。
夜は寝たい人物
警察官と夜勤は切り離さない関係です。
警察官として採用されると警察学校の過程を得て地域警察官として勤務をします。
地域警察官は主に交番で勤務をするのですが夜勤があります。
警視庁は4交替制ですから、4日に一回は夜勤です。
県警は3交替制から3日に一回は夜勤があります。
どちらも仮眠時間が設けられていますが、事件や事故のため休憩が取れない場合が多くあります。
著者が配属された警察署は繁華街を管内に受け持っていたので、仮眠できることのほうが珍しく、24時間以上寝れない状況は少なくありませんでした。
地域警察官に限らず内勤(刑事や交通部門など)に入ろうと夜勤は存在します。警視庁では内勤を8班に分けているため8日に一度は夜勤です。
地域警察官よりも内勤の警察官が超過勤務時間(残業)が圧倒的に多い事実から、交番勤務より過酷であることが伺えます。
さらに、階級を上げても夜勤は存在します。
ですから、睡眠時間を確保したい人物は警察官を勧めません。

「内勤の方が楽だし、泊まりの日はきちんと仮眠できる!」なんてことはありません。むしろ内勤のほうが劣悪な労働環境です。
警察官の多くは「寝れない環境」に「慣れる」のですが、なかにはその環境に適応することができず体調を崩したり勤務中に寝てしまう警察官も存在します。
警察官である限り「夜勤」は存在するため「体質的に受け付けない」人物は警察官として働くことは難しいでしょう。
また、人間には睡眠が健康には欠かせません。三代欲求の一つたる睡眠を蔑ろにする警察官の仕事は非常に不健康です。
長生きしたいのであれば警察官は適さないでしょう。
お金を稼ぐのが好きな人物

お金を稼ぐことが好きな人は退職する傾向が多いです。
警察官は公務員ですから、インセンティブによる利点は少ないです。
個人の仕事量や努力に限らず支給される給料は一定ですので、お金を稼ぐことに対する工夫は必要ありません。
公務員は与えられた仕事をすることで評価をされる社会であるため、奇想天外な刺激や既存の仕事ではなく新しいことに取り組みたい人物は警察官としての仕事に面白みを感じないでしょう。
そのため、生涯において予想ができる給料を貰う環境から、お金を稼ぐことが好きな人物は自分が好きなことが制限される職場であると感じます。
これは、著者の経験ですが、私もお金を稼ぐことが好きな人物でした。
このような感覚で警察官の仕事をしていると、変わらない給料から「必要最低限の努力」をしようと考えるようになります。
つまり、仕事に対するモチベーションが無くなるのです。
誰もが同じ給料を支給されるのであれば「サボったほうがマシじゃない?」的な感覚です。
警察官は仕事に対する「気持ち」が評価される側面から、給料や見返りとは異なる「やりがい搾取」が風潮として存在します。
なので、仕事に対する原動力(気持ち)を「お金」と位置付ける人物には公務員は適さないのです。
さらに、警察官は副業が禁止です。
お金を稼ぎたい人物は自由に「何か」をする傾向にあります。
そのため、お金を稼ぐことが好きな人物は副業等のビジネスに手を出します。
そもそも、公務員は副業が禁止ですから、そのリスクや副業による楽しさから警察官の仕事から離れるのです。
他にも、株や投資が好きな人物も警察官を退職する傾向が多いように感じます。
著者の経験からですが、懲戒等の問題を抱えて退職する人物を除いて、他の警察を退く人物の多くは株や投資をしていました。
公務員は株や投資は禁止されていないので、これを理由に懲戒等の処分はありません。
おそらく、株や投資が好きな人物は「どうすればお金を稼ぐことができるのか」を自分で考えることが好きな傾向があるので、警察官の仕事とは相性が合わないのでしょう。
チームワークが苦手な人(一人が好きな人)

警察官の仕事は人間関係が特に重要です。
警察官の仕事はチームワークです。
イメージとしては、サッカーやバスケなどのチームスポーツが当てはまります。
交番で勤務する場合は、相勤員(一緒に勤務する人)と退勤まで同じ空間で働きます。
他の仕事であれば、出勤から退勤までの長くて八時間が同僚や上司と共に過ごす時間ですが、警察官の場合は勤務時間が長いことから二十四時間以上特定の人物と接する場合があります。
また、その距離感も近いです。
仮眠や食事などの休憩も同じ交番で取るため、衣食住を共にします。
事件や事故で現場に臨場する場面でも、他の勤務員との連携は欠かせません。
物理的な距離感の他に、仕事にもチームワークが求められます。
書類を作成する場合でも、一つの事件や扱いを複数名(係)で処理するため、密接なコミニケーションを要求されます。
なので、警察官の仕事は、時間的に、物理的に、仕事の内容的に、他の職業よりも人との関わりが重要になるのです。
このような人間関係に主軸がある職場の雰囲気として、一人でいることに対する理解が得られない欠点があります。
そのため、常に複数人で行動することが求められるのです。
それは、勤務時間外でも例外ではありません。
著者は警察学校を卒業してから寮生活を数年経験しましたが、休日や寮で過ごす時間は一人になることを大切にしていたことで、周囲からは変わり者として見られていました。
上司との面談において「一人で過ごす時間が好きである」と伝えても同僚と交流する機会を設けるように強制されました。
もちろん、これが勤務時間内であれば賃金が生じている理由から円満な人間関係を築くことは義務となります。
しかし、仕事の範囲で賄うことができないツケを労働者の私的な時間を削り支払わせる行為に正当性はありません。
人間関係の構築が仕事に求められているのであれば、その過程は労働なのですから然るべき対価を労働者に支払う義務があります。
それを怠り仕事に必要な工程を労働者が補填する仕組みが異常であると考えます。
警察の職場に限らず、日本の雇用体制は労働者に甘えた挙句に不利益な関係性を正常な状態であると認識させることに優れているのです。
この傾向が顕著にある職場は警察です。
そもそも、警察官の職場環境は「群れる」ことが好きな人物がほとんどです。
最近流行りの言葉で表すと「陽キャ」の集団です。
休日などプライベートの時間も関係なく職場の人間と接することが求められます。
単身者であれば寮生活なので、二人部屋なんてこともあります。
警察官の職場では、これらが「好きな」人物が多いので「単独行動」をする人物のほうが少数です。
そのため、自分の時間を大切にしたい人物は警察官の職場環境に耐えられないと思います。
プライベートを充実させたい人物
警察官として働くのであれば、プライベートを犠牲にする覚悟が必要です。
まず、警察官として採用されると、そこから5年間は寮生活です(警視庁)。
さらに、日常生活のあらゆる場面で制約が課されます。
交際者がいる場合、車を購入する場合、旅行に出かける場合、様々な場面で上司の許可が必要です。
他にも、勤務時間外に出勤を強要されます。
警察官は、職務の内容から体力が不可欠です。
そのため、出勤時刻の1時間前に柔道や剣道の稽古を強要されます。
休日には、各種検定や研修、訓練でプライベートの時間を削られるのです。
ここで驚くのが、これらの時間に給料は発生しません。
こんな環境が罷り通るのが警察です。
寮生活やプライベートに関する詳細は以下の記事で触れます。
日々の生活に課せれる制約の他にも、警察官として働く上では、他人とプライベートに関することを享有する場面が多く存在します。
警察官の仕事は「人との関わり」が重要です。
その理由は、職場での良好な人間関係の構築が仕事のクオリティに結び付くからです。
「良好な人間関係」を構築する手段としてコミニケーションが挙げられるのですが、仕事に関する会話のみでは関係性を促進するには不十分です。
そうすると、必然的に仕事には関係ない会話で盛り上がる場面が生まれます。
仕事に関係しない会話とはプライベートに関する内容です。
警察官の仕事は上下関係が厳しいことから、仕事以外でも、その関係を強要される状況が多く、プライベートに関する内容でも、その風潮から上司の意見や指摘を尊重しなければならない場面が存在します。

例えば、「〇〇の趣味はオススメだから経験しろよ」とか「お前は彼女がいないんだから〇〇をしろよ」等です。
こんな、プライベートに関する内容までも干渉してくる環境が警察です。
結婚すると衣食住や家族のことまでアレコレと言われます。
さらに、これらの指摘やアドバイスに関して否定的な意見を示すと職場の空気感が悪くなることから、下の者はプライベートの指摘やアドバイスにも従う必要があるのです。
そんなありがた迷惑な行為を「面倒見が良い」と考えている人物が多いのが警察組織の特徴です。
これと同じく、飲み会や職場のレクリエーションを強制されたりします。
著者は、飲み会が苦手なのですが、職場で飲み会に参加しないことで異常者扱いされたのは今でも記憶に残っています。
勤務終わりは毎回のように先輩に連れられて飲み会や娯楽場に出向き、非番では警察寮の共用スペースに集まり出前を注文し雑談、休日も職場の人間と出掛ける生活を強要されました。
このような公私混同が当たり前であると考える人物が大多数の警察では、ワークライフバランスやプライベートの充実を求める人物は歓迎されません。
職場の人間と密に関わる「アットホーム」であることを強要される環境が好きであるのならば警察の職場は適任でしょう。
著者のように、これらに対して嫌悪感を抱く人物は警察官として働くことを推奨はしません。
なので、過密な人間関係を強要される環境が苦手な人物は警察官として勤め上げることは難しいように感じます。
警察官の転職事情
警察官は転職する上で市場価値は高いのか。転職に向けた対策や警察官の仕事により身に付いた技能は活かせるのか。これらの疑問を解消する内容です。さらに、転職先や転職する時期などを著者の経験を交えて解説します。
警察官の転職時期

まずは転職時期について触れます。
結論から述べると「可能な限り早い時期」に退職することを勧めます。
その理由は、警察官としての経験は他の業種で役に立つことが少ないからです。
日本の企業はキャリア形成を考慮して長期間において同じ環境で働くことの想定をしています。
そのため、中途採用においても「若い」人材が重宝されるのです。
中途採用本来の制度趣旨を解釈すると、求職者の年齢は問わず、その専門的な技能や能力を評価して雇い入れるものでした。
ですが、警察官として務めた経験により身に付くスキルは、あくまで警察の仕事上でしか通用しないものです。
なので、警察官が中途採用本来の制度を利用して転職することは勧められません。
さらに、警察官は平均水準よりも給料が高く、中途採用は前職の給料を考慮して待遇を定めている場合もあるので、人件費が嵩む能力が低い人材をあえて採用するメリットは少ないでしょう。
これらから、キャリア採用や中途採用よりも第二新卒としての市場価値が残されている段階で転職することを勧めます。

「可能な限り早い時期」にも例外があります。
それは、警察学校に在校している警察官です。
著者は元警察官ですので警察学校の生活を経験しています。
そこでは、同期が数十人余り退職する状況を見てきました。

警察学校に在校中の間は退職を勧めません。
その理由は、後悔が残るからです。
警察学校では、現場の警察官が行う仕事を何一つ経験することができません。
警察学校に入校する以前は少なからず警察官の仕事に憧れや興味を持っていたと思います。
ですが、警察学校に入校したことで、その仕事を経験出来るわけではありません。
そのため、退職後も「警察官として仕事を続けていたら」との「もしも」の自分を考えるそうです。
さらに、警察学校で退職してはならないもう一つ理由は、警察官としての適性があるかどうかの判断ができないことにあります。
警察学校での経験、それに伴う「辛さ」、現場での経験、それに伴う「辛さ」、警察学校で必要とされる人物、現場で活躍する人物、それぞれ異なります。
警察学校の環境と自分が「合わない」との理由で、警察の適正がないと判断することは時期尚早です。
もしも、警察学校の厳しい環境から「辞めたい」と考えているのであれば「実務修習」を経験してからでも遅くはないと思います。
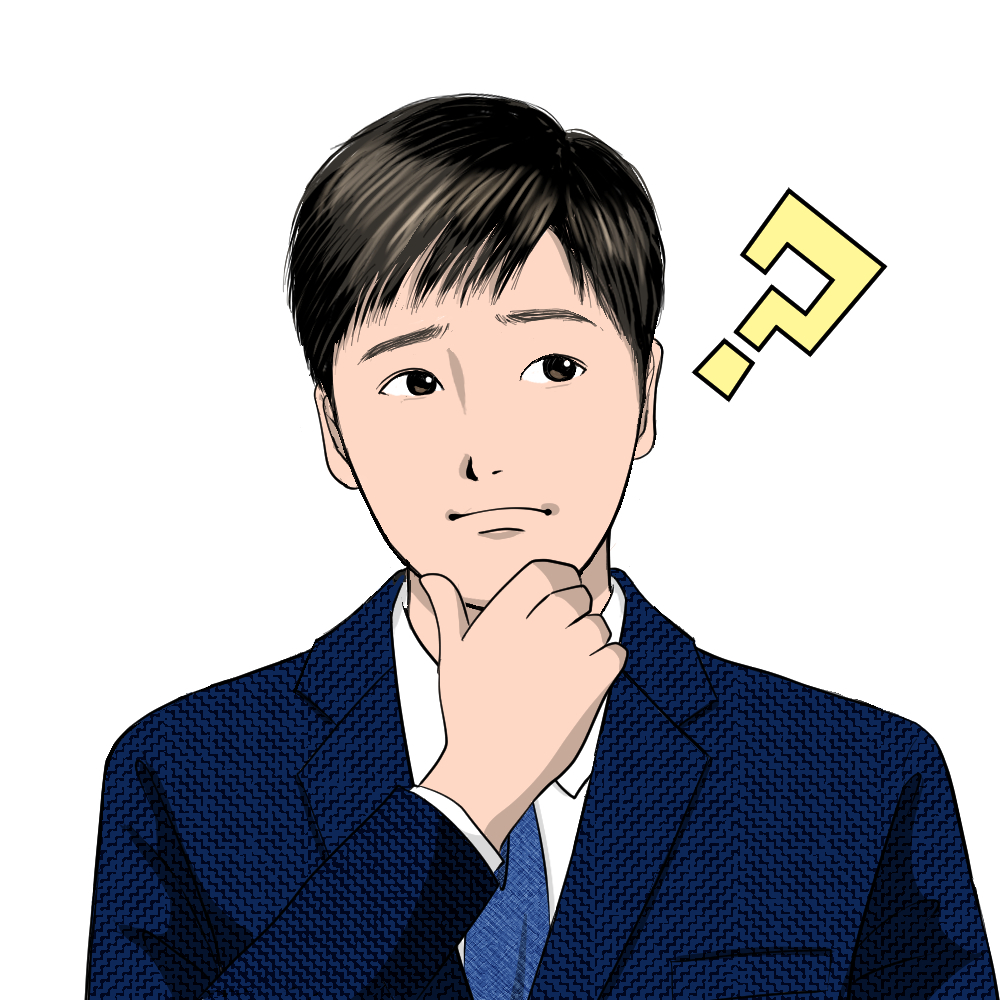
警察学校を途中で辞めたら転職でデメリットになる?
特にデメリットにはならないでしょう。
ですが、警察学校を卒業した後で退職をすると「警察学校を耐えたんだ」と転職活動時にアピールするポイントが増えます。
もちろん、その効果は転職先の業種にもよります。
中には「警察学校の生活にすら耐えられないんだからウチでは雇えないよ」と評価されることも。
はたまた「警察学校での経験なんてウチでは関係ないから」と歓迎される場合もあります。
どちらにせよ、警察学校での経験が大きなデメリットやメリットになることは少ないと思います。
警察学校を途中で辞める場合、「警察官なんて絶対ヤダ」と気持ちの整理が出来ているのであれば警察学校に在校中であっても「可能な限り早い時期」に退職するべきでしょう。
警察学校は大卒なら六ヶ月、高卒なら十ヶ月です。
その間に退職するのであれば、第二新卒として就職活動ができるので、より転職活動には有利となります。
警察官の市場価値
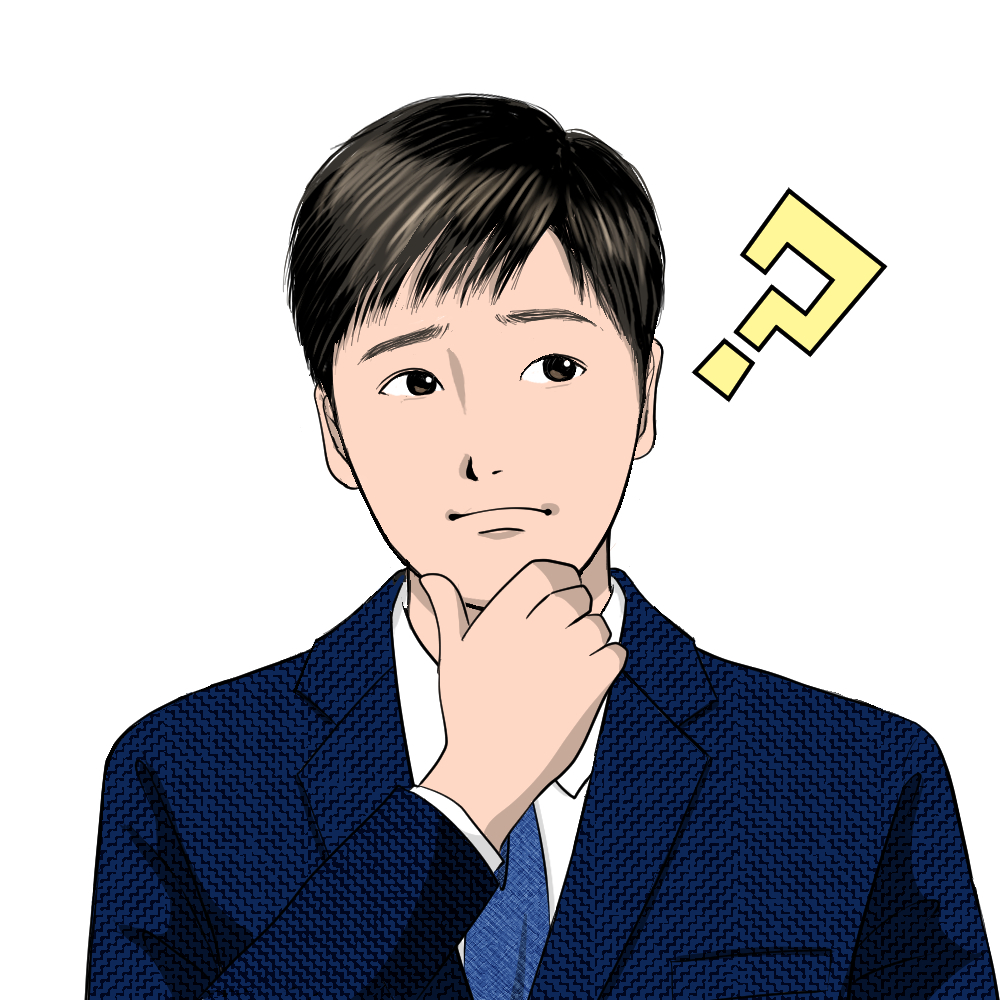
警察官としての経験は転職先で役に立たないの?
役に立つことは少ないです。
もちろん、業務内容や組織形態が警察と類似する企業や組織であれば警察官としての経歴は重宝されるでしょう。
また、従業員の信頼性や身分の潔白性を重んじる企業や組織も警察官を欲します。
しかし、警察官の給料水準と同様の待遇で中途採用している企業は、警察官を雇うことに特段の意義を見出してはいません。
転職において、警察官としての経験で「役に立つ」ことは基本的にはありません。
社会人としての一般的な技術や能力、例えばパソコンの使い方(Excelや Word)や器材(コピー機とか)の扱い方は、転職先でも通用するスキルではありますが、警察官のみならず、他の転職者(誰しも)も「当たり前」に身に付けている能力です。
そのため、「役に立つ」スキルとして取り上げるべきものではありません。
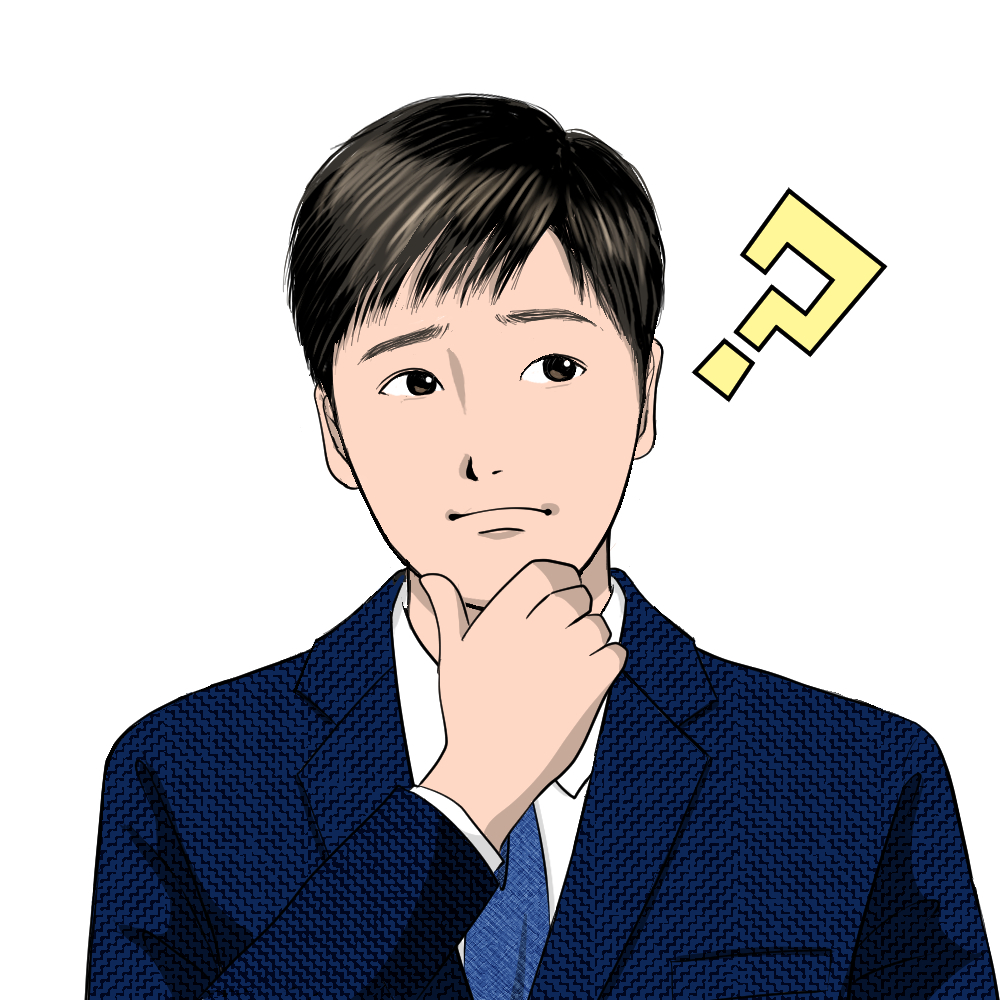
警察官は転職で不利なのか?
一概にそうとは言えません。
警察官には転職時に強い武器があります。
それは「話題性」と「信頼性」です。
就職活動における「面接」では、第一印象が大事だと言われています。
それは「話」の「掴み方」も含みます。
つまり、「初めの話」がつまらなければ面接官は「その他大勢」のうちの一人として求職者を無意識で括り分けをします。
警察官としての経験は、他の業界人からしたらブラックボックスであるため興味を持つ対象でもあります。
そのため、転職する企業や組織の人事にアピールする話題性に長けているのです。
多くの求職者は、自己の経歴に「特出する点」がないため「その他大勢」として埋もれてしまうのですが、話題性がある「警察官」であるのならば「掴みの部分」で目立つことができます。例えば、営業部門から採用されたいのであれば、掴みとしての話題から顧客を得ることができるのだと言うことを話術を通して面接官や人事にアピールすることで評価に繋がります。
他には「信頼性」です。
警察官のような社会的に信用が高い仕事に就いている人物は守秘義務等の規則を遵守するのだと評価される傾向があるため、会社における枢要の地位に雇い入れたいと考える組織は少なからず存在します。
また「信頼性」を求めている企業や組織は数多く存在しており、言わば「警察と雰囲気が近いお堅い仕事」では「警察官」はかなり優遇されます。
ですが、「信頼性」については「なぜ退職したのか」を明確に説明できなければ「問題を起こしたから辞めたのかのな」と在らぬ疑いを掛けられることも。
実際に著者は転職時に「自身の潔白」を証明することに苦労しました。
警察官から民間企業に転職する場合に企業の採用側から「警察官をなんで辞めたの?なにか後ろめたい理由があるのかな」と懐疑的な見られ方をする状況はかなり多いと言えます。
これら「なぜ退職したのか」に対する正当な理由を説明することができれば大きなアドバンテージになります。
転職の対策
警察官として転職活動に身を投じる上で一番の対策は「可能な限り早く転職する」ことです。
警察官としての経験は他の業界で重宝されるものではありません。
時間の経過とともに自分の市場価値が下がります。
その他の対策として挙げられることは、技能や資格を会得することです。
技能は語学やITに関すること、資格は国家資格等の市場を独占できるもの、これらの勉強を勧めます。
警察官として勤めていると講習や研修等の制度から語学やITを公費で学べる機会があります。
資格に関しても同様ですが、転職で活かせるものは少ないのが現状です。なので、空いた時間を活用して独学で勉強に励む方法もあります。
警察官は、資格取得のため私的で検定等を受験する場合には許可が必要なのですが、退職することを念頭にしているのであれば従う道理はありません。
警察官として転職活動をする上で注意しなければならない事項が二つ存在します。
それは、必ず現職中に転職活動をするということです。
警察は転職先が決まってから退職しましょう。
そもそも、警察官は転職に不利な側面が多く転職活動が成就するとは限りません。先行きが不明確なまま退職をすると資金が底をつく可能性や現職警察官というアドバンテージも活かせません。
二つ目の事項は転職することを誰にも言わないことです。
これは、同僚には不用意に話すなとの意味ですので、職場とは関係がない人物に相談することは構いません。
職場の人間に転職することを話すと間違いなく止められます。
その場は、励ましてくれたりと心地が良い環境かもしれませんが、結果としてタイミングを逃すことにも繋がります。
さらに、警察の特徴たる「ありがた迷惑」な周囲の指摘やアドバイスが判断や選択を鈍らせます。
警察の組織や仕事が「合わない」ことを理由に退職するのに、その「合わない」人達のアドバイスや指摘を受け入れるようでは「合わない」警察官の価値観に染まる転職活動をするようなものです。
なので、職場の人間に転職するとの内容を話すことは勧めません。








コメント