警察官の採用試験で落ちる理由を大きく分けると三つに収束できます。
学力試験や体力試験、さらには、身辺調査を含む書類選考では本人の努力や外的な要因による影響が大きく、合否に至る過程を明確に解析することが可能です。
しかし、二次試験における面接は、勉強や努力では乗り越えられない場合があります。
著者の考えではありますが、面接における具体的な対策は「知ること」が重要なように感じます。
その面接で重要である「知ること」について、誤った認識を持ち試験に挑む受験生が多いので本記事を書きました。
本記事では、二次試験で落ちる三つの理由をまとめました。
さらに、詳細の解説は第三章を参照してください。

本記事では、警察官の採用試験で落ちてしまう原因をまとめました。
今回は二次試験や面接で求められている人物像を主軸に解説をします。
①素直な人物か?
警察では馬鹿を欲しています。
その理由は、馬鹿は管理が容易だからです。
警察官の仕事に高度な能力は求められていません。
そのため、優秀な人物よりも、管理が容易な人材が重宝されます。
さらに、警察は行政機関です。
行政とは立法の指針を実現する手足です。
手足の役目を担う行政は、立法的な作用である「思考」を必要としません。
では、これら行政を担う人物に相応しい特徴とは。
それは「素直」や「真面目」な人物です。
警察官の試験では、体育会系の人物や真面目な人物が合格します。
そのため、面接の場面で「優秀な人材」だとアピールすることは逆効果となります。
警察官の採用面接を担当するのは、当然ですが警察官です。
また、採用に関わる人事課の職員が面接を担当するのではなく、各所属の幹部職員(階級が高い人事課とは異なる警察官)が試験のため派遣されて面接官として対応します。
なので、面接を担当する警察官は、現場で共に働きたい人物を自らの職場と照らし合わせている場合が多いのです。
そうなれば、部下として雇いたい人物の特徴は、警察の慣習を踏襲している人物、物事に疑問を持たずに黙々と指示を聞く人物、これらが評価の対象となります。

警察官の試験で陥る罠はここにあります。
変に賢さを演じるよりもアホそうにしていたほうが得策です。
そもそも、面接では「自分という商品」を市場に売り出す場面なのですから「良い商品」であるほどに価値が付くはずです。
ですが、それは一般的な市場の原理で、就職活動における市場では、「良い商品」が必ずしも売れるとは限りません。
市場には買い手が存在します。商品である人材を購入するために買い手である企業は対価を支払うのですが、その対価が買い手の資金力としての環境やリスク(商品を管理する能力)なのです。
「良い商品」を購入しても扱えなくては価値を見出すことはできません。
さらに、就活市場における商品としての人材は、買い手次第でその価値が変わります。
それが、適正です。
買い手により変貌する商品価値は「良い商品」が市場で「適当」な値段を付けられる保証はなく、時には「粗悪品」が「良い商品」として市場の需要を満たす状況も存在するのです。
就職活動における市場では、その企業や組織にとって「良い商品」であるか、これが重要です。
警察官の試験で結果を残せない人物は「良い商品」であることに執着しているように思えます。
そんな「良い商品」であることを望む人物は、職業の適正である「なれる」と「むいている」を混同しているのではないのでしょうか。
・論理的思考
・客観性
これらを思い浮かべた人物は危ないです。
たしかに、客観性や論理的思考は警察官には欠かせません。
なので、これら能力に長けた人物は採用試験でも重宝されるはず。
しかし「向いている」とは理想的な状態を言います。
目標の状態と現実は異なります。
これら目標や理想は、行政を統括する立法、さらにはその主権者たる国民に帰属する標準化された意思に基づく総称です。
つまりは「こうであってほしい」と人々が思い描く状態が「向いている」との意味です。
警察の組織構造は、官僚制による円滑な統治機能の維持に指針を置いています。
そのため「素直」や「真面目」 な人物を組織に組み込んでいるのですが、その弊害として「向いている」よりも「なれる」が優先されるのです。

警察の組織が欲している人物の特徴が「なれる」です。
就職活動では、中途半端に賢い人物に限って社会の需要を考慮した結果から理想の状態を投影して面接でその人格を演じてしまいます。
罠はここにあります。
「理想の警察官像」これを面接で押し出すのです。
これでは、実際の状態から「働く仲間」を集めている採用側との間にギャップが生じてしまいます。
なので「理想の警察官像」 である「向いている」を考えるよりも「なれる」を意識してみましょう。
警察官等の職種では「若い人材」が求められます。
「若い人材」は社会を知らないため「扱い易い」のです。
特に警察官は上司の命令に従うことを前提として職務が遂行されるのですから「変な癖」が染みついた「新人」よりも、社会を知らない「真っ白」な「新人」を育成することにメリットがあります。
年齢を重ねた人物よりも「若い人材」のほうが環境に順応する能力が長けていことから、就職活動の市場では新卒で学生を採用するのです。
②危険人物ではないか?
次に、危険性です。
警察官は保安職です。
なので、意味不明な人物を採用したくはありません。
理由は、警察官として雇うリスクがあるからです。
一般的の企業や会社であれば多少のリスクは背負い込むかもしれません。型破りの手法やアイディアが時には重要な場合もあるので、ハイリスクハイリターンを容認している環境も存在します。
しかし、警察組織が求めている人材とは、平均的なポテンシャルを有する「普通」の人間です。
リスクを抱えて「普通」ではない人物を採用する必要性がありません。
そのため、採用試験においてリスクとされる言動を面接又は適性検査で露見されると大幅な減点に繋がります。
著者は、採用に関する業務の経験はありませんが、警察官の面接における採点基準は択一的なものです。
大勢の受験者が面接を受けるのですから、面接官の主観で採点されるようでは不平等が生じます。
さらに、面接官は人事課の職員ではなく各所属の幹部警察官が派遣されて面接を実施しているので採点にはマニュアルが必要です。
そのため、機械的な採点ができるように面接試験を最適化しています。
詳細な採点基準は分かりませんが、おそらく「質問」に対する「返答」に数段階の評価を定めた択一的な配点が設けられています。
他にも、減点項目や加点項目など、ある発言や用語、言動に対応した一覧表から受験者の特出した傾向を評価する仕組みであると考えられます。
例えば、減点項目に「サバイバルゲーム」と記載があり、受験者の「趣味はサバイバルゲームです」との回答からマイナスの評価をする仕組みがあるのではないかと予想しています。
なので、択一的な採点基準で面接を評価される仕組みから「余計な発言をしない」ことが重要であると思います。
③根本的な勘違い (重要な箇所です)
面接対策における根本的な勘違いについてお伝えします。
以前とある学生から質問されました。
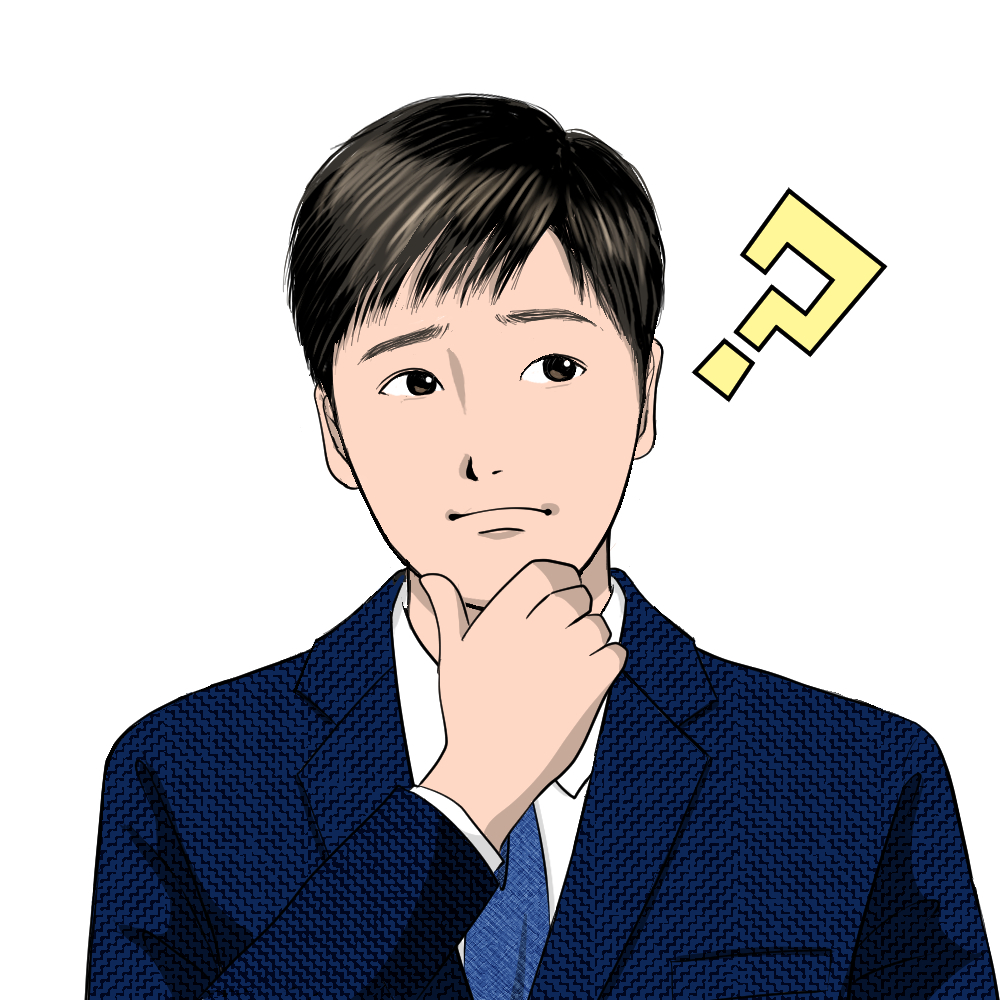
不合格の理由はなんですか?志望動機について助言してください。
彼は不機嫌そうにしていました。
そして想定問答のメモを見返しながらブツブツと…。
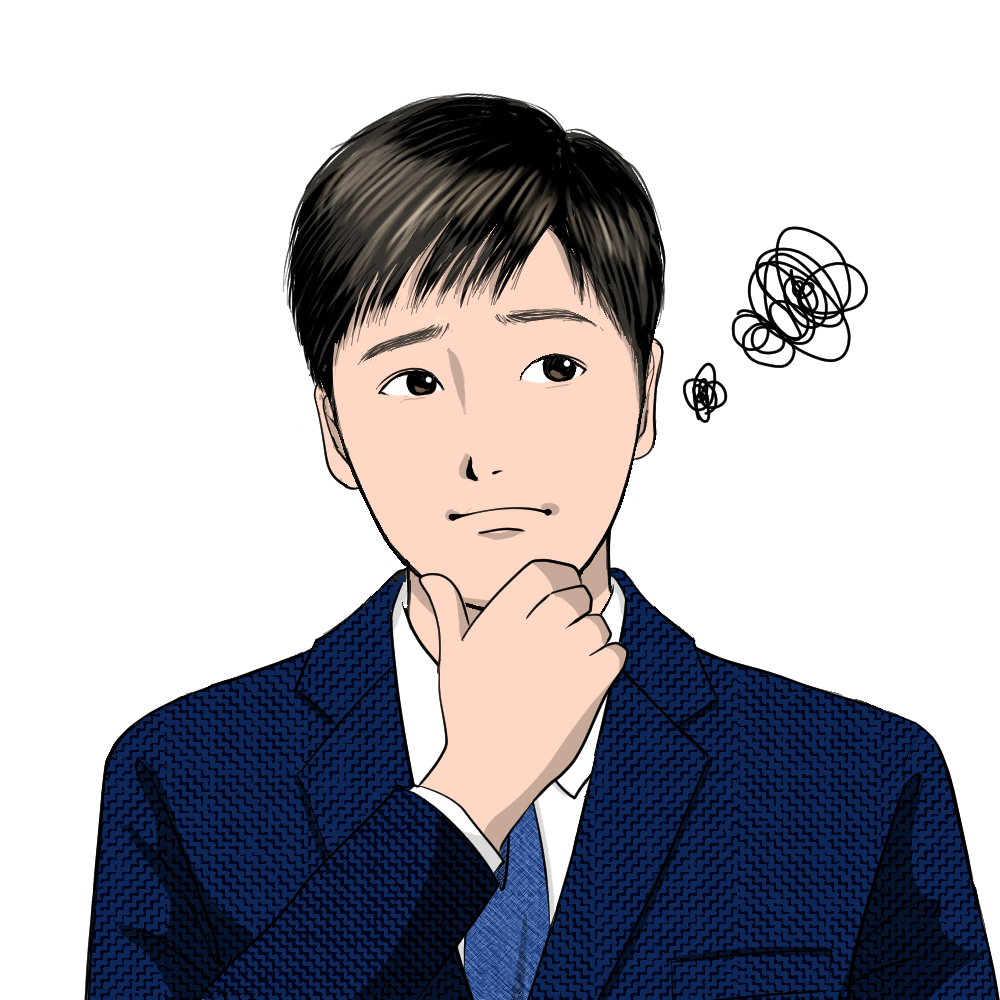
どこが間違っているんだろう。どこも問題がない内容だと思うんだけどな。。。
要するに「採用面接の質問にきちんと返答できたのに結果は不合格だから納得できない」このような主張がしたいのでしょう。
このような学生は、採点試験に落ちた理由を根本から勘違いしています。
その勘違いとは、警察官の採用面接においては、質問に対する返答(内容)が重要ではないことです。
もちろん、最低限の返答(内容)をしなければなりませんが、それ依然に「言動」「喋り方」「表情」「立ち振る舞い」「雰囲気」要するに「性格」を把握することに主眼を置いた「面接(質問)」なのです。
おそらく、面接官の択一的な採点基準(「②危険人物ではないか?」を参照してください。)にも「ハキハキしている」等の項目が設けられているのでしょう。
ですから(「②危険人物ではないか?」)に抵触しない範囲おいては、個々の質問に対する想定問答の添削は適度で十分です。
著者が実際に見てきた学生の多くは誤った対策をしていました。
面接で質問される内容の返答を充実させようとそればかりに力を入れているのです。
このような受験者は、面接官に論理的に、正確に、博識的に、内容を伝えるかを考えています。
しかし(「①素直に命令に従う人材か?」)から言えるように、そもそも、警察官に「なる」ために優れた知能は必要ありません。
むしろ、知的で優秀な人物ほど嫌悪される環境ですから、このような対策では本末転倒です。
警察官の仕事は「誰でもできる」ものです。
なので、そんな仕事では甲乙つけがたい評価に代弁して「気持ち」が人物を評価する指標上で重要になります。
そのため、こんな組織の性質からも、物事の本質や内容より「気持ち」や「性格」などの表面上の項目を評価に内在させている警察の面接では「内容」よりも「表面上のもの」が重要視される傾向は明らかです。

想定問答の作成や添削はほどほどで十分。
肝心なことは「演技」です。
実際に模擬面接を行うと質問に対する返答(内容)のみは完璧で他は杜撰な受験生が大勢います。
内容はロジカルだが、喋り方がぎこちない、目を見て話さない、暗い、声が小さい、例を挙げるとキリがありません。
面接は「言動」「喋り方」「表情」「立ち振る舞い」「雰囲気」これらを見極める手段なのです。
手段と目的の転換
本来の質問の意義:日常生活での質問は内容(返答)を目的にします。時間を尋ねられたら時刻を答えるように、内容(時間)を把握する手段として質問しているのですから時間を知ること(内容)が目的になります。
しかし、採用面接では質問の返答(時間を答える)が手段に変わることがあります。そのため、目的は内容(返答)ではなく、そこ(返答)に至るプロセスまたは反応を確認することが面接官が求める(知りたい)意義となります。
警察官の面接は、面接官と受験者の質問と返答のやり取りを通して「人柄」を見極めています。
試験の対策をせずに合格する人物がいます。
その理由は警察が求めている「人柄」と「その受験者の性格(人柄)」が合致した場合には、ぶっつけ本番でも合格できます。
なので、そこに「知識」を始めとする「想定問答」は不要なのです。
この原理からも採用面接で受験者が述べる「内容」よりも、それを通して面接官が見極めるであろう「人柄(性格)」が重要であると言えるのです。
面接で(「①素直に命令に従う人材か?」)を「演じる」ためには「元気が良い」「目が輝いている(将来への嘱望)」「声量」これらを意識しましょう。
イメージは「明るく元気な野球部員」です。
(追記)著者が経験した出来事を話します。
先日のことです。
とある学生に質問されました。
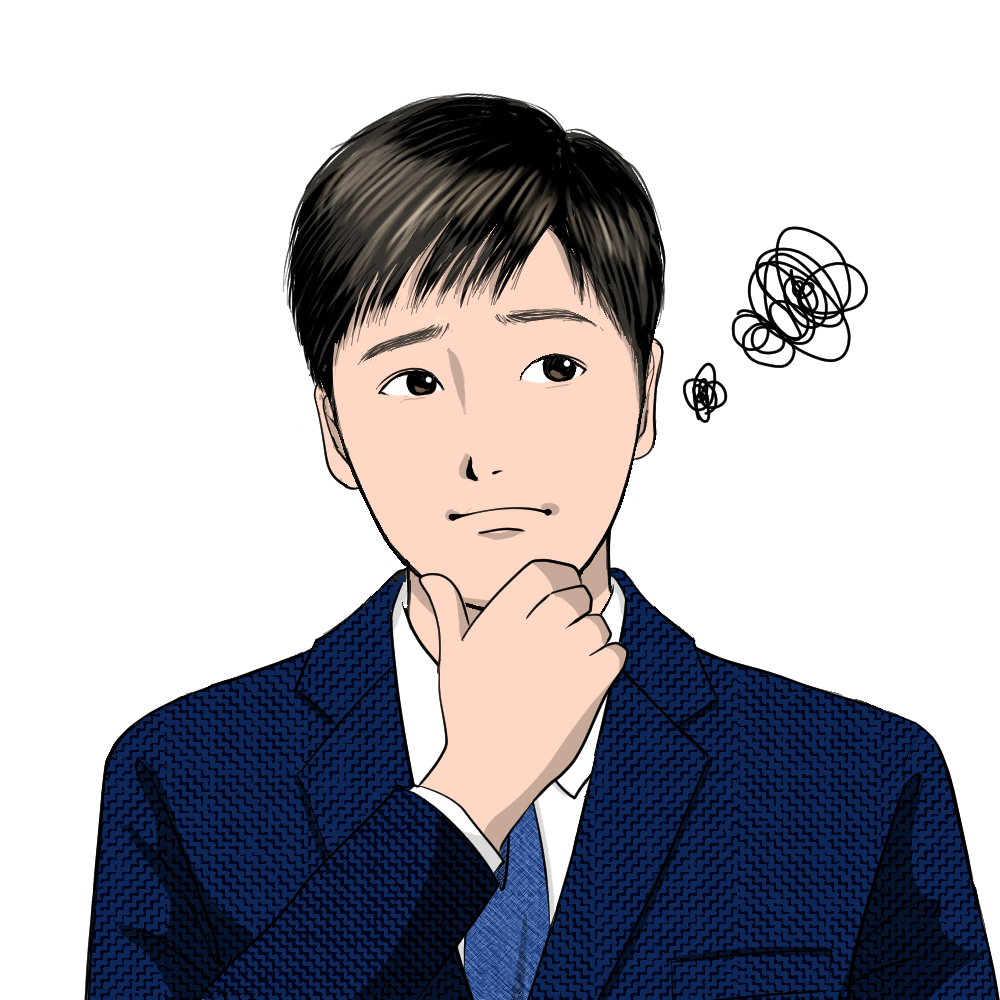
面接も手ごたえがあったのにどうして不合格なのですか?
このように。
私は思いました。
警察官採用試験の本質を理解していないのだと。
面接で喋れる事は二の次です。
さて、質問してきた学生は自身の特徴を把握していませんでした。
その学生は、オタクっぽい外見が特徴です。
まさに、不合格の原因はそこにあります。
立ち振る舞い、喋り方、容姿、言動、これらが不合格に繋がるのです。
そして、質問してきた彼は、その事実に気が付くことは無いでしょう。




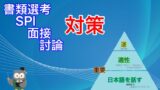
コメント