警察官採用試験は一次試験と二次試験のプロセスに分けられます。 一次試験では主に学力や教養力を図るための筆記試験、二次試験は面接や体力測定、身体検査など、警察官としての適性や職務に耐えられる人物であるかの見定めを行います。 一次試験を合格した人物のみが二次試験を受験する資格を得られるため、まずは、一次試験の内容である「筆記試験」の対策が必須です。
警察官採用試験は一次試験と二次試験のプロセスに分けられます。 一次試験では主に学力や教養力を図るための筆記試験、二次試験は面接や体力測定、身体検査など、警察官としての適性や職務に耐えられる人物であるかの見定めを行います。 一次試験を合格した人物のみが二次試験を受験する資格を得られるため、まずは、一次試験の内容である「筆記試験」の対策が必須です。
一次試験の内容について
警察官の採用試験は各都道府県の警察が別々に実施をしています。そのため、試験の内容や実施項目に「若干」の違いがあります。
受験する前には必ず該当する都道府県警察の採用ページから試験内容の詳細を調べるようにしましょう。
一般的には、警察官採用試験における一次試験の内容は以下の項目です。
| 教養試験 | 一般教養及び政治、社会、法律、経済等の知識、文章理解、判断推理、数的処理、資料解釈、図形判断、人文科学、社会科学、自然科学、一般科目などが出題範囲です。 | 五肢択一式 50問 試験時間 2時間 |
| 論文試験 | 警察官に関する論題又は自身の経験に関する論題が主に出題されます。 | 1題 試験時間 1時間20分 |
| 国語試験 | 記述式(読み30問:書き30問)※警視庁のみ実施 | 60問 20分 |
| 適性検査 | マークシート方式による検査です。 | 調査中 |

それぞれの試験の対策は以下の記事で解説します。
漢字試験(国語試験)の対策は過去問をひたすら解きましょう。その他にも、漢字検定2級から準1級の難易度の問題が出題されるため漢字検定のテキストを使用する勉強方法も効果的であると言えます。
各種試験の合格点
合格点は倍率と関係するため、受験する各都道府県警察により異なります。また、受験する年度によっても変わります。
受験生の試験結果の平均が高ければ、それだけ合格点は引き上げられますし、反対に受験生の試験結果の平均が低いのであれば合格点数の基準は下がります。
さらに、警察官の採用試験は資格認定試験とは異なるため「〇〇点以下」は不合格などの明確な基準はありません。あくまで、総合的な点数を吟味した上での合否です。例えば、柔剣道の世界大会で優勝した人物の教養試験の点数が低いことを理由に一律に不合格にすることはありません。なので、定められたボーダーは存在しないのです。
そのため、以下の基準は「あくまで」参考程度に過ぎません。
| 教養試験 | (ボーダーライン)20点以上 | (安全圏内)25点以上 |
| 国語試験 | (ボーダーライン)40点以上 | (安全圏内)45点以上 |

上記の例はあくまで平均的なボーダーラインです。続いては最低得点で合格した事例を見ていきましょう。
| 教養試験 | 11点 |
| 国語試験 | 30点 |
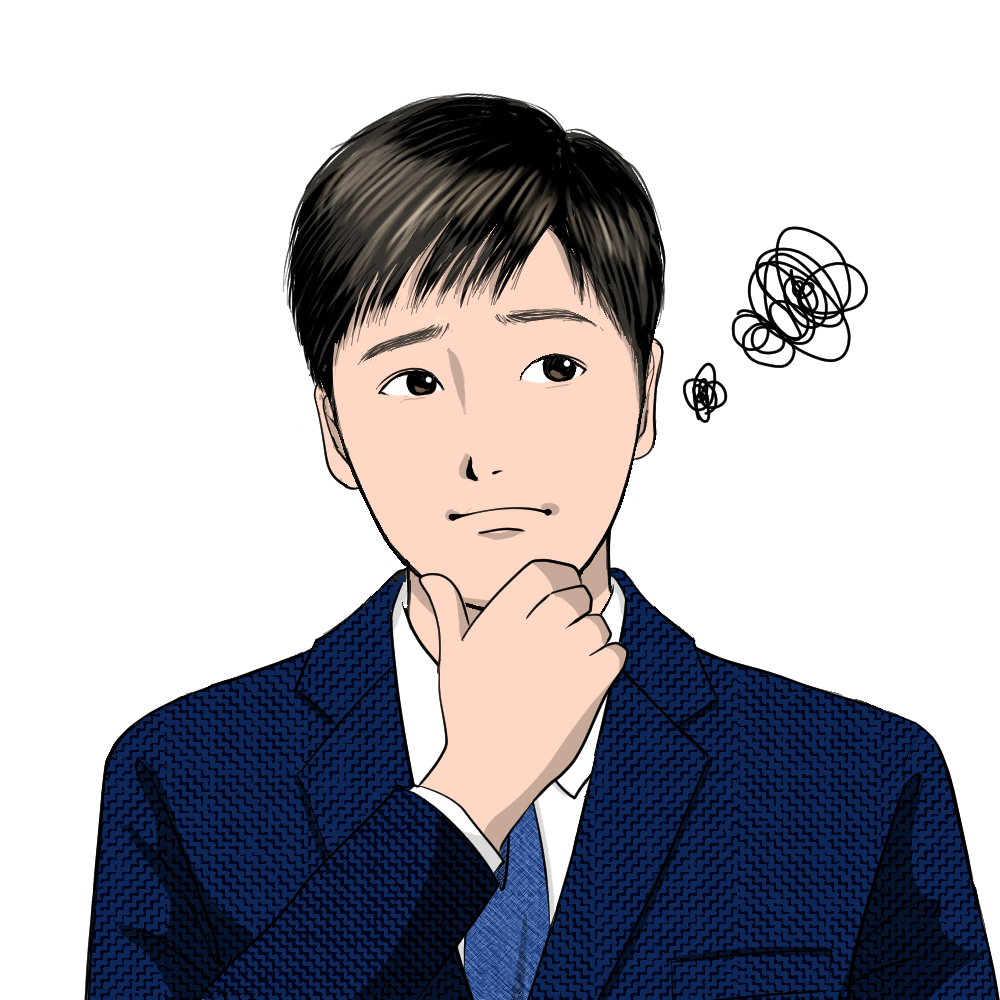
警察官の試験は一回目試験と二回目試験、三回目試験に分かれてるよね。それぞれ、合格するボーダーに違いはあるの?
警察官の採用試験は、その年度に一回のみ実施されるわけではなく複数の試験日が設けられています。
その複数の試験日は第一回目試験、第二回目試験、第三回目試験、等の名称でそれぞれエントリーすることができます。さらに、第一回目試験の採用結果が発表される前に第二回目試験の募集が開始されるため併願して応募することも可能です。警視庁の採用試験では、第三回目まで試験が実施されますが、その実施回数は各都道府県警察により異なりますので注意が必要です。
基本的には、その年度の初めに実施される第一回目試験が採用人数が多く倍率も低いと言えます。そのため、警察官を目指すのであれば第一回目の試験に挑戦することを薦めます。
各種試験の合格点に関しては、第一回目試験のボーダーは前述した通りですが、第二回目以降は採用定員が絞られるため倍率が上がります。そのため、第二回目試験は第一回目試験のボーダーよりも「プラス5点から10点」と考えましょう。第三回目試験も同様ですが、体感的には第二回目試験よりも難易度が高いような気がします。そのため、ボーダーは設けずに可能な限り高い点数を取りましょう。
一次試験の採点方法
合否は一次試験全体の総合的な点数により決まります。教養試験、論文試験、国語試験 適性検査、更に当日実施される資格加点や受験生の経歴(スポーツ歴等)、その他の事情から鑑みて合否が判定されるのです。その他の事情に関する内容は「高得点でも不合格な理由」で解説していきます。

資格加点に関する記事は以下を参照してください。
筆記試験が高得点でも不合格な理由

以下の記事で解説しています。
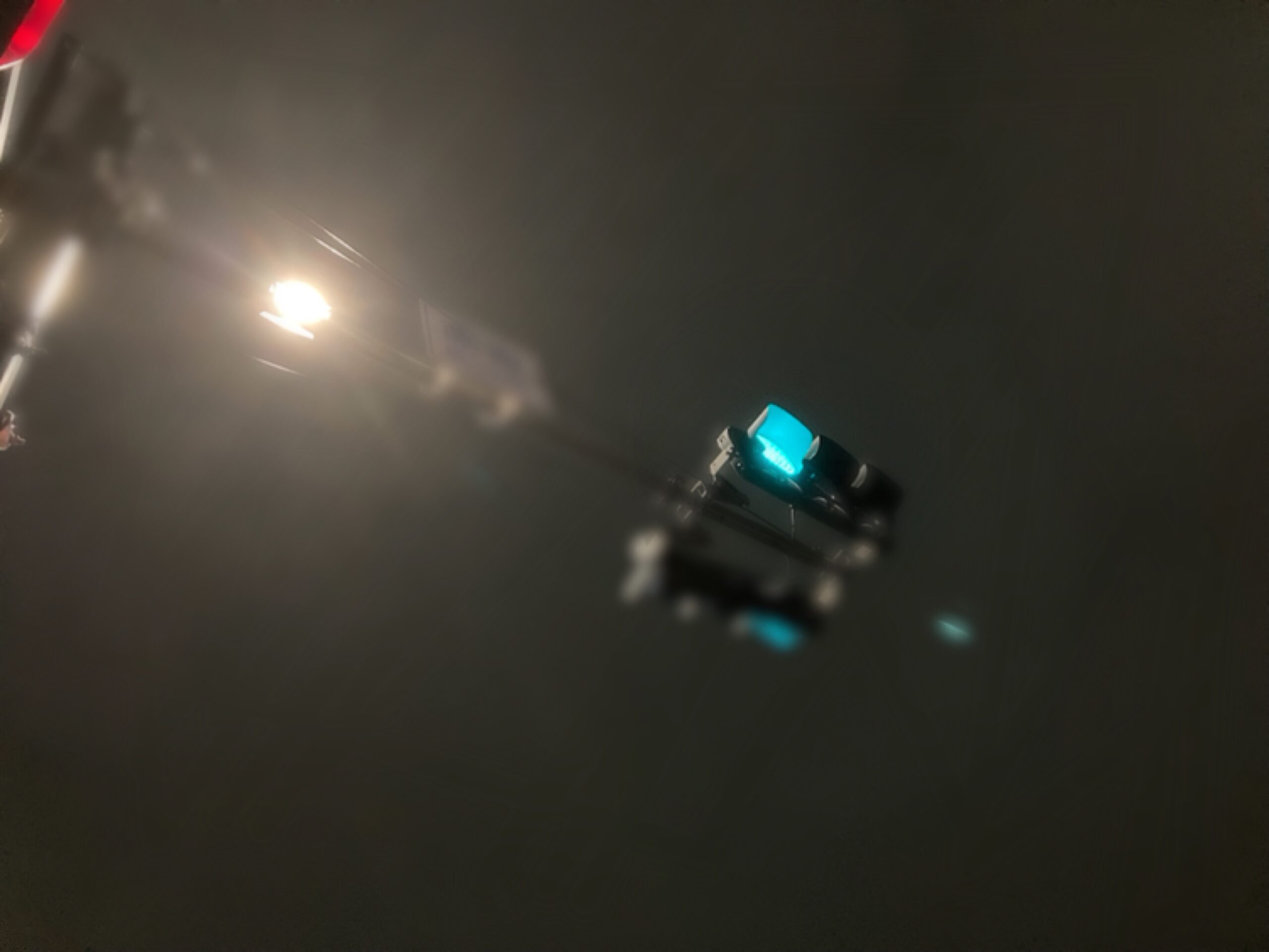



コメント